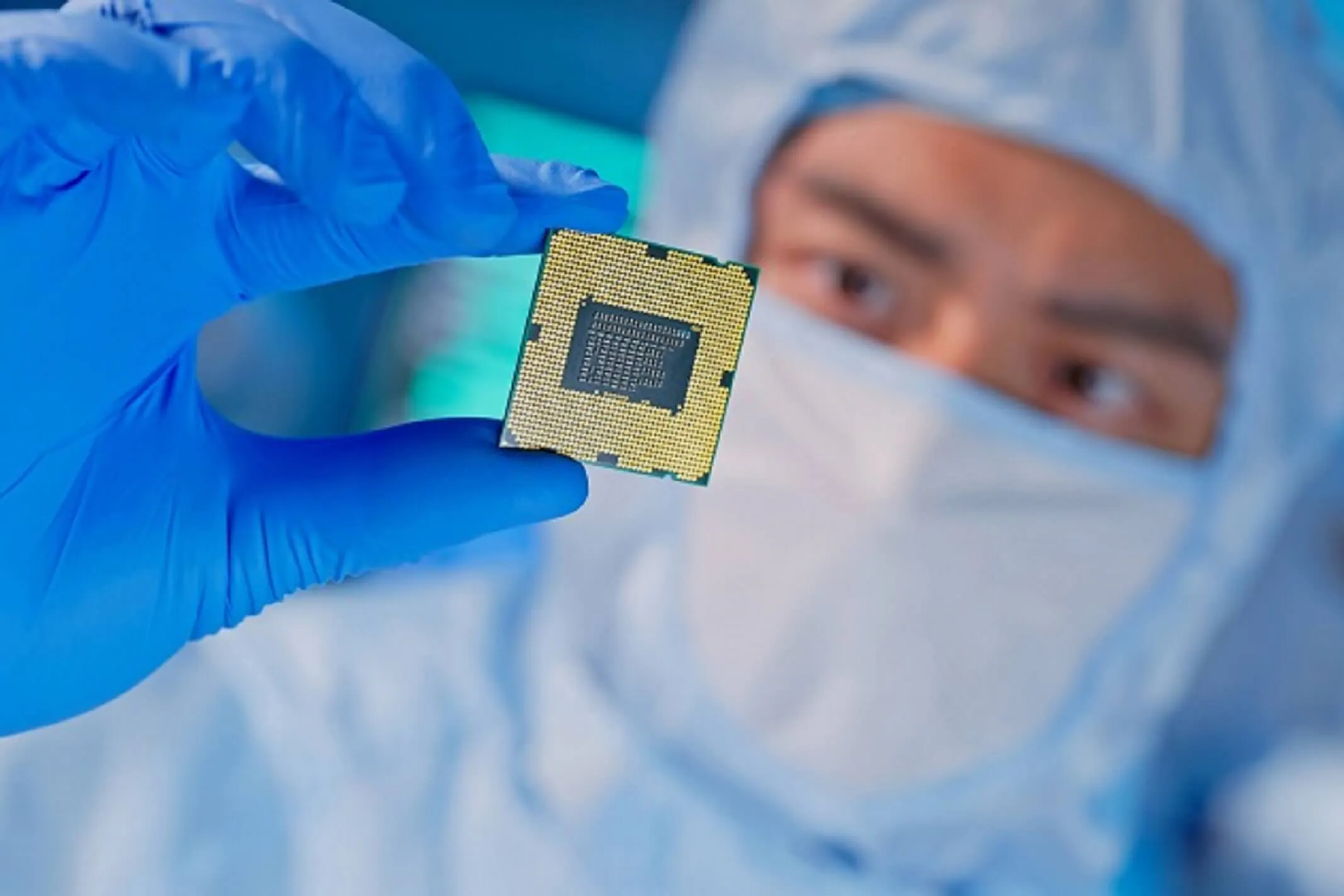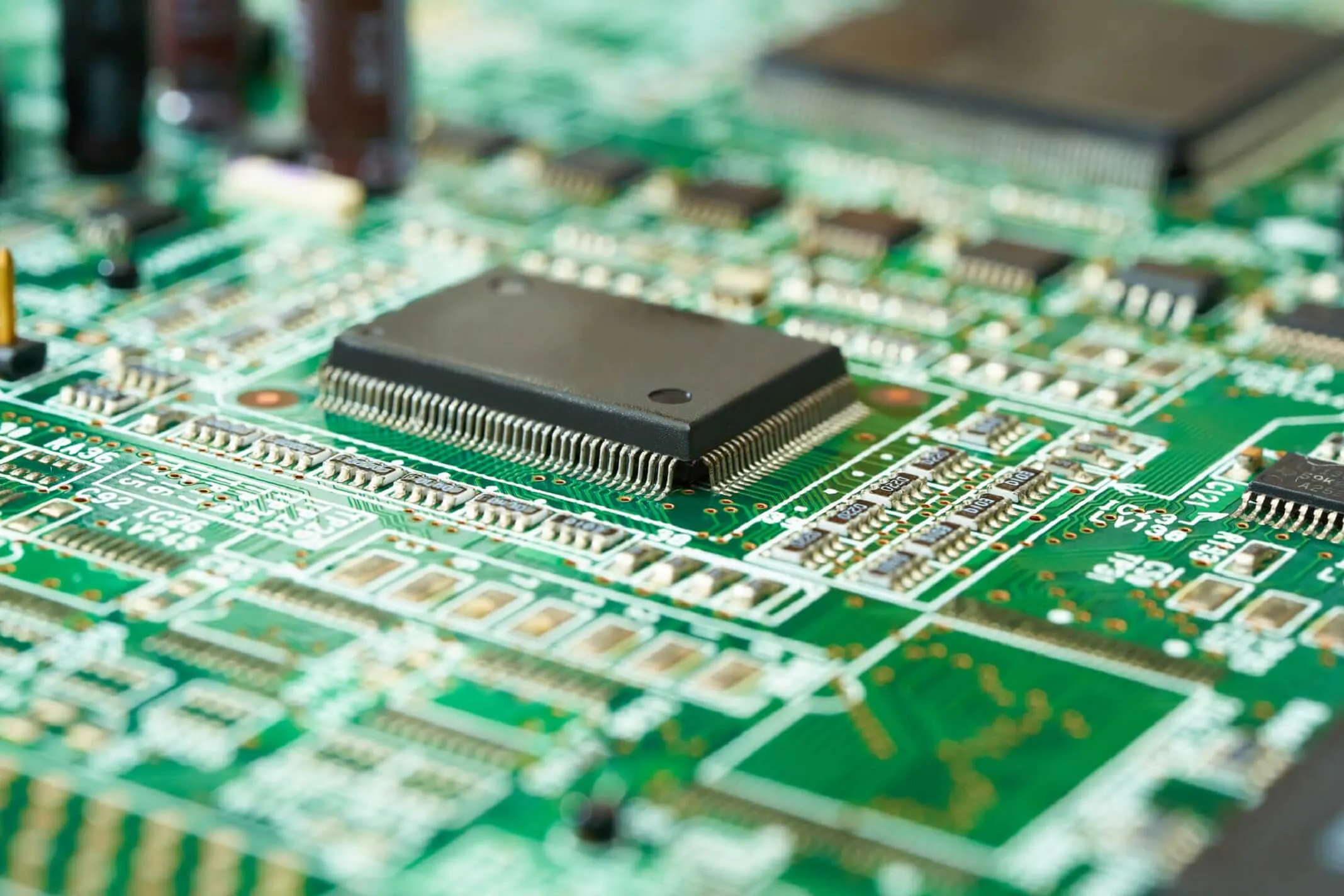夜勤の仕事は生活リズムが乱れやすい!睡眠や食事のポイントを紹介

日中に眠り、夜働くという勤務スタイルの「夜勤」。
深夜手当がつくので給料も高く、「これから夜勤の仕事をしてみようか」と考えている人もいるのではないでしょうか。
夜勤で働くときに気をつけたいのが、生活リズムです。
夜勤は、昼間の仕事と比べて生活リズムが乱れやすい傾向にあります。
この記事では、夜勤で生活リズムが乱れることのリスクや、夜勤で働くコツについて紹介しています。
夜勤前に眠れなかった時の対処法も紹介しているので、これから夜勤の仕事をしようと考えている人は参考にしてください。
夜勤の仕事は生活リズムが乱れやすい

夜勤は、昼間働くよりも体に負担がかかりやすい働き方です。
なぜそれほど負担がかかるのかといえば、その理由として生理的要因と社会的要因があげられます。
生理的要因としては人間が本来持っている睡眠欲求による影響があげられます。
人は体内時計によって、1日の睡眠リズムを調整しています。
夜になると体温が低下して、自然と睡眠欲求が高まるものです。
いっぽうの社会的要因とは、社会の仕組みが原因となる場合です。
社会の24時間化にともない夜働く人も増えているものの、まだ昼間に働く人を中心に世の中が動いているという現状があります。
家族が昼間活動している場合はとくに、睡眠や活動のタイミングが家族のペースに合わせることになりがちです。
このように生理的要因の観点からも、社会的要因の観点からも、夜勤で生活リズムが崩れやすくなるのは必然だといえます。
夜勤には2種類ある

夜勤の仕事は、夜勤専属とシフト制に分けられます。
どちらの夜勤タイプかによって、気をつけるポイントや生活のリズムも変わっていきます。
それぞれの特徴を確認しておきましょう。
夜勤専属
夜勤専属は、常に夜勤という働き方です。
夜に働いて昼間に眠るというスタイルになり、仕事も休日も昼と夜が完全に逆の生活リズムになります。
慣れてしまえば、毎日同じペースで活動できるのが専属夜勤の良いところでしょう。
ただ病院や役所関係の手続きなど、日中に用事を済ませたいときは、普段寝ている昼間の時間に活動する必要があります。
その場合は生活リズムを乱さないよう、日中に仮眠の時間をとるなど工夫が必要です。
シフト制
シフト制は、日によって勤務時間帯が変わる働き方です。
シフト制勤務には、2交代制と3交代制があります。
【2交代制】 日勤・夜勤の2交代制。10時間勤務で休憩が2時間といった勤務体系。 【3交代制】 日勤・準夜勤・夜勤の3交代制で8時間勤務が一般的。 |
シフト制の場合は、「日中活動して夜は寝る」というスタイルを基本としつつ、夜勤の日に生活リズムを崩さないように工夫する必要があります。
夜勤で生活リズムが乱れることのリスク

夜勤で生活リズムが乱れると、さまざまなリスクがあります。
ここでは、夜勤で生活リズムが乱れることによる、精神的な影響と肉体的な影響について解説します。
精神的な影響
睡眠不足になると、精神面にも影響が出ます。
脳は、起きているときに様々な刺激を受けて活性化しますが、眠ることで脳を落ち着かせて疲れを取ります。
睡眠不足になると、脳の疲れを十分にとることができません。
疲れが残った状態で働くことになるので、仕事の効率が悪くなり、思考力も下がるというリスクが増えます。
記憶の定着は睡眠中に行われるため、睡眠不足が続くと物覚えも悪くなります。
睡眠不足でストレスがたまり、ストレスによって眠れなくなるという悪循環に陥る可能性もあるでしょう。
肉体的な影響
睡眠中は成長ホルモンが分泌されます。
傷ついた細胞を修復したり、体の疲れを回復するために必要なのが、成長ホルモンです。
睡眠不足が続けば、体の疲れは取れません。
睡眠不足で成長ホルモンが十分に分泌されなければ、疲れが取れないだけではなく、肌荒れにも繋がります。
寝不足からくる疲労や肌荒れが原因で、老けて見られるようになる可能性もあるでしょう。
夜勤が多い仕事の生活サイクルの整え方

生活リズムが乱れやすい夜勤の仕事ですが、働くのであれば、できるだけ生活サイクルを乱さない工夫が必要です。
夜勤が多い仕事で生活サイクルを整えるコツを紹介します。
仮眠をとる
可能であれば、夜勤途中に仮眠をとりましょう。
ベストな仮眠の時間は2時間程度です。
2時間の睡眠であれば、しっかり深い眠りを取りつつ、ちょうど眠りが浅くなったタイミングで起きられます。
短時間でも質の良い睡眠時間となるでしょう。
夜勤前に光を浴びる
夜勤の前に光を浴びることで、眠りを誘うメラトニンというホルモンの分泌を抑制できます。
光の強さは2500ルクスで蛍光灯8本くらいの明るさ、光の波長はブルーライトともいわれる青色光がおすすめです。
夜勤前に光を浴びることで、体に「起きて活動する時間だ」と錯覚させ、生理的要因でもある「日中に活動して夜は眠る」という生活リズムを変えることができます。
夜勤明けの食事にも配慮を
夜勤明けは、糖質が少なく消化の良い食事を心がけましょう。
疲れていると甘いものが欲しくなりますが、寝る前に甘いものを食べると太りやすくなります。
夜勤明けに食べるのであれば、野菜が多めの味噌汁や消化しやすい鶏肉やゆで卵などがおすすめです。
甘いものが食べたいときは、お菓子やパンを避け、フルーツをとると良いでしょう。
食べ過ぎると、消化にエネルギーを使ってしまい眠りの質が下がるので、あまり食べ過ぎないことも大切です。
睡眠環境を整える
日中寝るときは、良質な睡眠を確保するために、睡眠環境を整えておくことも大切です。
外の光が入らないように遮光カーテンをしたり、家族の生活音が気にならないように耳栓やアイマスクを使うのもおすすめです。
耳栓が苦手な人は、静かな音楽を流してもよいでしょう。
眠りやすいように空調を整えたり、締め付けの少ない服装で寝ることも重要です。
睡眠前の習慣に注意
寝る前にカフェインやアルコールをとる習慣がある人は注意が必要です。
カフェインやアルコールには覚醒作用があるので、寝る前に摂取すると、寝つきが悪くなったり睡眠の質を下げることにもなりかねません。
就寝前のカフェイン・アルコールはやめましょう。
寝付けなくても横になって目をつぶる
その日の体調によっては、スムーズに寝付けないということもあるでしょう。
そんな時は、横になって目をつぶるだけでも脳を休ませることができます。
眠れないからといって焦ると、緊張感から余計に眠れなくなることもあります。
寝付けないときは焦ることなく、布団に入って横になりましょう。
睡眠をとれなかったときの対処法

日頃どんなに睡眠に気を使っていたとしても、眠れなかったり睡眠時間が足りなくなることもあるでしょう。
夜勤前に十分な睡眠が取れなかったときのために、対処法も確認しておきましょう。
口を動かす・会話をする
声を出すことで脳が活性化します。
周りの人と会話できる状況であれば、話をすることで一時的に眠気が収まるでしょう。
周りに人がいなかったり、会話できる状況にないときは、口を動かすだけでも脳への刺激となります。
ガムを噛むのもおすすめです。
ガムを噛み脳内神経伝達物質のセロトニンが分泌されることで、眠気が覚めやすくなります。
冷たい水で顔を洗う
仕事中に眠くなった時や、仮眠からすっきり起きられない時は、冷たい水で顔を洗うのもおすすめです。
冷たい水で顔を洗うことで、交感神経が優位になり頭がすっきりするでしょう。
体を動かす
体を動かすことでも、交感神経を刺激することができます。
軽いストレッチがおすすめですが、仕事中でストレッチできない場合は、その場で手足を動かしたり、足踏みしたり、軽く動き回るだけでも良いでしょう。
少し動くだけでも体温があるので、体を活動モードに切り替えることができます。
どうしても眠れないときは医療機関で相談を

眠れない日が何日も続くようだと、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
免疫力が下がって体調を崩しやすくなるほか、うつ症状が出ることもあります。
どうしても眠れないという時は、内科や診療内科などの医療機関に相談しましょう。
適切な治療を受けることで、睡眠不足や体の不調が改善されることがあります。
また万が一睡眠不足による体調不良で退職することになった場合にも、在職中の受診履歴があることで、失業保険を受けやすくなります。
まとめ
夜勤で働いていると、睡眠のとり方が難しく、睡眠不足になりがちです。
睡眠不足が続くと、体調を崩したり、疲れが取れずに仕事の効率が悪くなることもあります。
夜勤で働く場合は、生活のリズムを崩さないことが大切です。
眠りやすい環境を整えたり、睡眠の妨げになる習慣をやめるといった工夫を取り入れましょう。
夜勤前に十分寝られなかったり、仕事中に眠たくなってしまった時は、今回紹介した対処法を参考にして乗り切りましょう。
どうしても寝られないという日が続く場合は、医療機関に相談することも選択肢として考えてください。