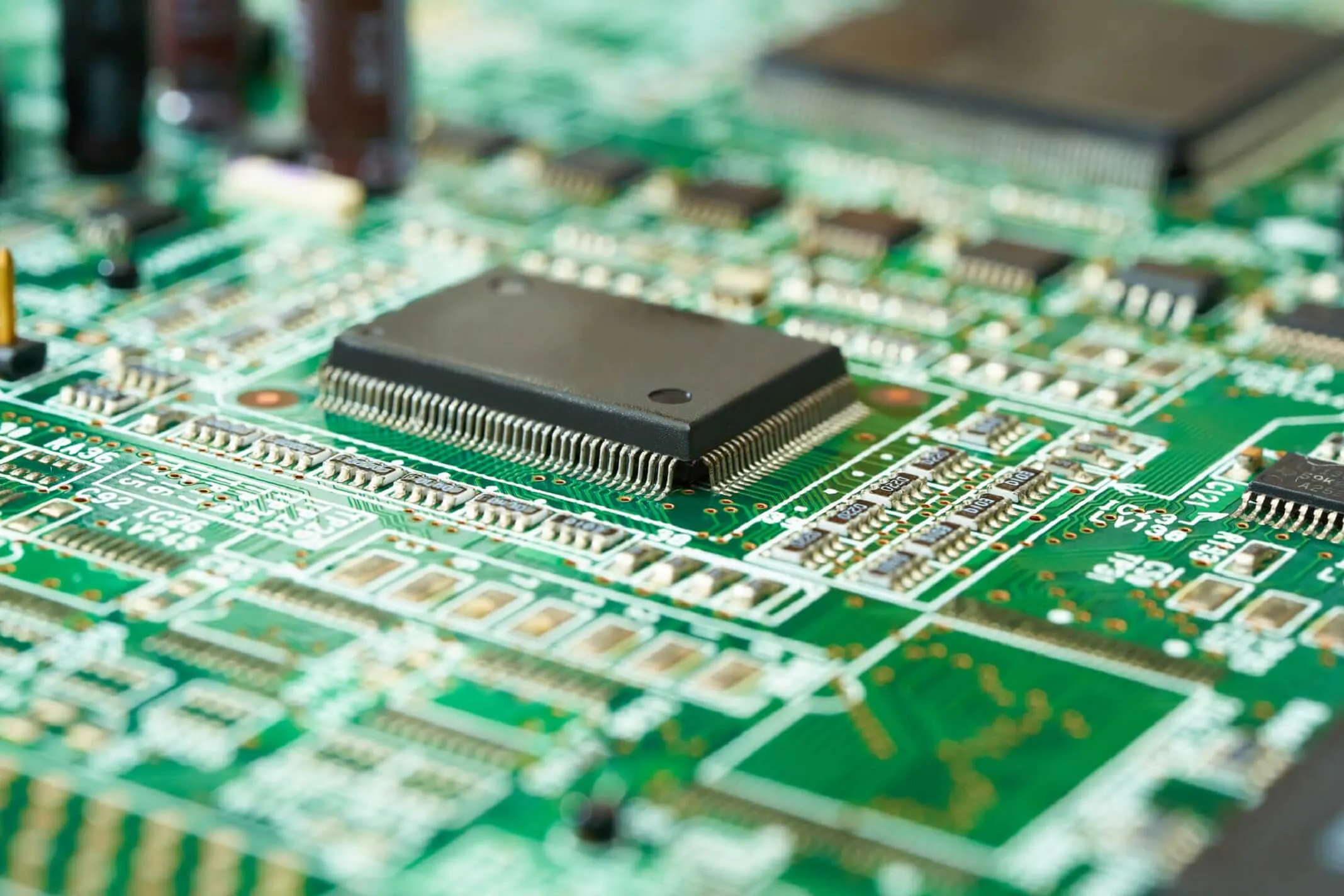工場勤務に役立つ資格とは|製造業に必要なおすすめの資格を詳しくご紹介!

工場に勤めている人は、業種によって種類はさまざまですが、いろいろな機械や設備を使いこなし、日々安全に気を付けながら仕事をこなしています。この中には資格がな�ければ扱えないものもあれば、資格がなくても作業ができるものなどいろいろです。しかし資格が必須であるかどうかに関わらず、工場勤務者は有資格者が多いのが現状です。
この記事では工場勤務者におすすめの国家資格や、国家資格ではないけれど取得しておくと有利なおすすめの資格を紹介しています。
資格を持っておくとメリットも多いので、自身のキャリアアップや転職のために資格取得を検討している人は最後まで目を通してくださいね。
工場勤務者が資格取得するメリット

工場勤務では資格は不要だと考えている人もいるかもしれませんが、実は資格を持っておくと有利であることが多いのも事実です。工場に勤務している人が資格を取得することで、以下のようなメリットがあります。
- スキルアップできる
- 評価・昇給につながる
- 転職がしやすくなる
実際にどのように役に立つのか、詳しく解説します。
スキルアップできる
資格を取得するということは、試験に向けて新しい知識や技術を正確に身に付ける必要があります。そのため資格取得のための努力が自然と自身のスキルアップにつながるのです。今現在の工場で扱う技術をさらに強化したり、または違う種類の資格を取得したりすることで、仕事の幅や見解が広がり広い視野を持つことができるでしょう。
評価・昇給につながる
資格を取得することによって、一定水準以上の知識やスキルを持った人であると認定されます。資格が必須でない工場であっても、その向上心や努力を上司や管理者から評価される可能性が高いでしょう。資格を持っていない他の社員との差別化ができるため、新しいポジションや昇給などにもつながりやすくなります。
高い評価を受けたり、昇給できたりすれば、自分の自信やモチベーションのアップにもつながるでしょう。
転職がしやすくなる
工場勤務者が資格取得すると、転職がしやすくなることもメリットの一つです。
資格は広く一般的に認められるスキルなので、社内だけでなく社外でも評価の対象となるでしょう。もし、転職をする機会があった場合でも、資格があるのとないのでは、採用時の評価にも違いが出てきます。特定の資格や難易度の高い資格があれば、転職時には大きな武器となります。
工場勤務・製造業で役立つおすすめの国家資格

資格には民間資格や国家資格など種類があり、中でも国家資格は国の法律に基づいて定められる資格です。そのため難易度も高い傾向にありますが、社会的な信頼も高い資格です。
工場勤務・製造業で役立つ国家資格には、以下のようなものがあります。
- 危険物取扱者
- 衛生管理者
- 電気工事士
- 電子機器組立技能士
- 機械保全技能士
それぞれの資格について紹介していきましょう。
危険物取扱者
危険物取扱者の資格は、国が定める危険物を取り扱う作業に従事する場合に、必要な資格です。この資格を持っているということは、該当の危険物に関する知識を持ち、適切に扱えることを証明できます。
危険物とは、消防法で定められた火災の危険性が高い物質のことで、医薬品や食品を扱う企業の他、ガソリンスタンドなどで危険物を取り扱う場合にも必要です。危険物には第1類~第6類までの六つの分類があり、危険物取扱者の資格は扱える危険物の種類によって、三つに分かれています。
- 甲種:第1類~第6類全ての危険物の取り扱いができるが、難易度は一番高い
- 乙種:試験に合格した種類の危険物のみ取り扱うことができる
- 丙種:第4類の危険物の一部しか扱えない
危険物取扱者の資格で最もメジャーなものは、乙種第4類です。第4類の危険物はガソリン、軽油、灯油、重油などが該当し、危険物全体の8割程度をカバーしています。そのため特殊な工場でない限りは、乙種第4類の資格を持っておくと汎用性があるでしょう。
◎危険物取扱者試験の概要
受験資格 | 甲:大学などで化学に関する学科を卒業したもの、大学で化学に関する授業科目を15単位以上修得したもの、乙種危険物取り扱い免状の交付後危険物取り扱いの実務を2年以上積んだものなど 乙・丙:特になし |
|---|---|
合格率 | 甲:33~42% 乙:65~71% 丙:48~54% |
難易度 | 甲:★★★★★ 乙:★★ 丙:★★★ |
試験内容 | 学科試験 |
衛生管理者
衛生管理者の資格は、労働安全衛生法で定められた国家資格です。衛生管理者は50人以上の従業員がいる工場や職場では最低でも1人は必要です。そのため衛生管理者の資格を持つ人材は工場や作業現場において需要があるでしょう。どの業界や職場でも重宝されるため、おすすめの資格の一つでしょう。
衛生管理者は、労働条件や労働環境の衛生面や疾病の予防措置などを担当することが主な業務です。
衛生管理者の免許には、以下の種類があります。
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
◎衛生管理者試験の概要
受験資格 | ・大学や高等専門学校を卒業したもので、1年以上の労働衛生の実務に従事したことがあること ・省庁大学校を卒業したもので、1年以上の労働衛生の実務に従事したことがあること ・高等学校や中高一貫校を卒業したもので、3年以上の労働衛生の実務に従事したことがあること ・10年以上の労働衛生の実務に従事した経験があるものなど |
|---|---|
合格率 | 第一種衛生管理者:43~46% 第二種衛生管理者:52~55% |
難易度 | 第一種衛生管理者:★★★★ 第二種衛生管理者:★★★ |
試験内容 | 第一種衛生管理者:関係法令、労働衛生、労働生理 第二種衛生管理者:上記から有害業務にかかるものを除いたもの |
電気工事士
電気工事士とは、住宅、ビル、工場などあらゆる建物の電気設備の工事を行える国家資格です。工場における電気工事士は、製品を生産するための機械や設備に関する工事を行うことができます。特に製造業においては、機械が止まり納期に遅れたり、市場の商品が品薄になったりすることを避けなければなりません。直接利益にも影響を及ぼすため、機械のメンテナンスや不良にいち早く気が付き修理するといったことは非常に大切で、重要な位置付けといえるでしょう。
とはいえ、電気工事は危険と隣り合わせであるため、資格を持った人しか行えません。
電気工事士の資格は工事範囲により、以下のように二つに分かれています。
- 第一種電気工事士(500キロワット未満の自家用電気工作物の工事)
- 第二種電気工事士(600ボルト以下の一般用電気工作物の工事)
◎電気工事士試験の概要
受験資格 | 特になし |
|---|---|
合格率 | 第一種電気工事士:62~64% 第二種電気工事士:65~72% |
難易度 | 第一種電気工事士:★★★ 第二種電気工事士:★★★ |
試験内容 | ・電気に関する基礎理論 ・配電理論および配線設計 ・電気応用 【筆記試験】 ・電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料および工具ならびに受電設備 ・電気工事の施工方法 ・自家用電気工作物の検査方法 ・配線図 ・発電施設・送電施設および変電施設の基礎的な構造および特性 ・一般用電気工作物および自家用電気工作物の保安に関する法令 【技能試験】 ・電線の接続 ・配線工事 ・電気機器・蓄電池および配線器具の設置 ・電気機器・蓄電池・配線器具ならびに電気工事用の材料および工具の使用方法 ・コードおよびキャブタイヤケーブルの取り付け ・接地工事 ・電流・電圧・電力および電気抵抗の測定 ・自家用電気工作物の検査 ・自家用電気工作物の操作および故障箇所の修理 |
電子機器組立て技能士
電子機器組立て技能士は国家資格であり、パソコンやスマートフォン、自動車や家電といった部品などの電子機器の組み立てや修理に必要な知識や技能を持つことを証明できます。特級、1~3級まであり、特級はマネジメント的な要素や計画立案などの作業試験もあるため、難易度が高いです。
◎電子機器組立技能士試験の概要
受験資格 | 特級:1級合格後、5年の実務経験 1級:7年以上の実務経験、2級合格後2年以上、3級合格後4年以上の実務経験 2級:実務経験2年以上、または3級合格者 3級:なし |
|---|---|
合格率 | 61.67% |
難易度 | ★★★ |
試験内容 | 電子機器、電子および電気、組み立て方、材料、製図、安全衛生 (特級:マネジメント、計画立案の作業試験) |
機械保全技能士
機械保全技能士とは、工場に設置してある機械の修理や定期メンテナンス、保全に関する業務を行います。電気工事士と異なるのは、電気に限らず、設備のメンテナンス方法や検査方法を学べる資格で、設備に関する幅広い知識を得ることができます。そのため、電気工事士と機械保全技能士を併せて取得しておくといいでしょう。
◎機械保全技能士試験の概要
受験資格 | 特級:1級合格後、5年の実務経験 1級:7年以上の実務経験 2級:実務経験2年以上 3級:なし |
|---|---|
合格率 | 特級:17.6% 1級:21.6% 2級:30.9% 3級:71.0% |
難易度 | ★★〜★★★★★★ |
試験内容 | 特級: 1〜2級:機械系保全作業と電気系保全作業、設備診断作業 3級:機械系保全作業と電気系保全作業の選択作業 |
工場勤務・製造業に有利な資格

国家資格以外にも、工場勤務・製造業で働く場合に有利な資格はたくさんあります。国家資格でなくでも、認知度が高い資格や需要が高い資格は多いため、持っておくと他の従業員と差別化して、評価されやすいというメリットがあります。
国家資格以外の資格には下記のようなものがあります。
- 溶接技能者
- フォークリフト運転技能者
- 玉掛技能者
- クレーン運転士
- 有機溶剤作業主任者
- 特定化学物質等作業主任者
- 安全管理者
- マイクロソルダリング(微細はんだ付)技術者
- CAD利用技術資格
- 機械加工技能士
溶接技能者
溶接技能者とは、溶接に関わる作業を行うときに、正確なスキルがあることを認定する資格を持っている人のことです。溶接の資格にはいくつか種類があり、工場で使われる溶接方法に合わせて資格を持っておくといいでしょう。
溶接技術者の資格には以下のような種類があります。
- アーク溶接作業者:放電現象(アーク放電)を利用して、金属同士を接合する溶接方法
- ガス溶接技能者:ガスを利用して溶接を行う方法
- 銀ろう付技能者:接合する母材より低い温度で溶けるロウを接着剤のように使用する溶接方法
◎溶接技能者試験の概要
受験資格 | 特になし |
|---|---|
合格率 | アーク溶接作業者:90%以上 ガス溶接技能者:80~90% 銀ろう付技能者:不明 |
難易度 | ★〜★★ |
試験内容 | それぞれの溶接方法に関する基礎知識、作業方法、関係法令 |
フォークリフト運転技能者
フォークリフトは工場や倉庫での運搬作業などに使われる自動車です。工場内での使用であっても免許が必要です。フォークリフト運転手の需要は多く、簡単に取得できるため、持っておくことをおすすめします。フォークリフトの運転免許は自動車学校など、都道府県の労働局に登録された教育機関で受講できます。
フォークリフトを運転できる資格には、以下の2種類があります。
- フォークリフト運転技能講習:最大積載荷重量が1トン以上のフォークリフトを運転できる資格
- フォークリフトの運転の業務に関わる特別教育:最大積載荷重量が1トン未満のフォークリフトを運転できる資格
特別教育は学科と実技のみで取得でき、修了試験がありません。そのため簡単に取得できますが、大きいフォークリフトが使えないことと、公道に出ての作業ができないことは覚えておきましょう。公道に出て作業を行う場合は、特殊自動車免許も必要�となります。
◎フォークリフト運転技能者試験の概要
受験資格 | 特になし |
|---|---|
合格率 | 90%以上 |
難易度 | ★ |
試験内容 | フォークリフトの走行装置、荷役装置、力学、法令 |
公式サイト | 各自動車教習所 |
玉掛技能者
玉掛けとはクレーンで荷物を吊り上げるときに、クレーンのフックに荷物を掛けたり、外したりする作業のことです。重いものを運ぶ設備がある工場などでは、玉掛け作業は必ずあります。玉掛け作業が安全に正確に行われていないと、途中で荷物が落下するなどして大きな事故につながることがあるため、工場にとって需要のある資格でしょう。
玉掛け作業の資格には以下の2種類があります。
- 玉掛け技能講習:吊り上げ荷重1トン以上の大型クレーンの玉掛け作業を行う
- 玉掛け特別教育:吊り上げ荷重1トン未満のクレーンの玉掛け作業を行うには資格は必要ないが、特別教育が望ましい
◎玉掛け技能講習の概要
受験資格 | 18歳以上 |
|---|---|
合格率 | 95% |
難易度 | ★ |
講習内容 | 【学科試験】 ①クレーン等に関する知識(1時間) ②クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識(3時間) ③クレーン等の玉掛けの方法(7時間) ④関係法令(1時間) ⑤学科試験 【実技試験】 ①クレーン等の玉掛(6時間) ②クレーン等の運転のための合図(1時間) ③実技試験 |
クレーン運転士
クレーン運転士とは、クレーンを運転するための資格です。工事や作業現場などで、重い資材などを持ち上げたり移動させたりさまざまなシーンで使われます。クレーンを運転する資格は2種類の免許と、技能講習、特別教育を受講する方法があり、それぞれ運転できるクレーンの種類が異なるため、自身の勤める工場で必要なスキルに合わせて、選択しましょう。
- ・クレーン・デリック運転士免許:移動式クレーンを除き、吊り上げ荷重5トン以上のクレーンを運転できる
- ・移動式クレーン運転士免許:吊り上げ荷重5トン以上の移動式クレーンを運転できる
- ・技能講習: 5トン未満のクレーンや、1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンを運転できる
- ・特別教育: 5トン未満のクレーンや、1トン未満の小型移動式クレーンを運転できる
◎クレーン運転士試験の概要
受験資格 | 18歳以上 |
|---|---|
合格率 | クレーン・デリック:60%(学科)、49%(実技) |
難易度 | ★★★ |
試験内容 | 【学科試験】 クレーンおよびデリックに関する知識 関係法令 原動機および電気に関する知識 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 【実技試験】 クレーンの運転 クレーンの運転のための合図 |
有機溶剤作業主任者
有機溶剤を使用する現場では、有機溶剤作業主任者の有資格者が現場の監督をしなければなりません。有機溶剤はさまざまな場面で使われるものですが、使用上の注意が必要なものが多く、一歩間違えると身体に害を及ぼす可能性もあるのです。有機溶剤の例としては、エチルベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムなどさまざまな種類があります。
◎有機溶剤作業主任者試験の概要
受験資格 | 18歳以上 |
|---|---|
合格率 | 90%以上 |
難易度 | ★ |
試験内容 | ・有機溶剤による健康障害およびその予防措置に関する知識 ・作業環境の改善方法に関する知識 ・保護具に関する知識 ・関係法令 |
公式サイト | 各都道府県の労働基準協会連合会 |
特定化学物質等作業主任者
特定化学物質等作業主任者は、労働安全衛生法に基づいて有害性が認められる化学物質を扱っている工場などで、作業者の人体に害が出ないよう、作業方法の指導や作業環境の改善を行います。特定化学物質や四アルキル鉛を製造したり使用したりする工場では、この資格を持っている人材を設置することが義務付けられているため、需要のある資格であるといえるでしょう。
特定科学物質等作業主任者は講習を受けるのみで取れる資格なので、取得しやすく取っておくといいでしょう。
◎特定科学物質等作業主任者試験の概要
受験資格 | 18歳以上 |
|---|---|
合格率 | 95%以上 |
難易度 | ★ |
試験内容 | ・作業環境の改善方法 ・保護具 ・健康障害 ・関係法令 |
安全管理者
安全管理者は、工場の作業場の巡回、設備や各作業員の作業方法などに、危険な場所がないかを確認し、危険なところがあれば安全防止策を講じることが主な役割です。製造業やガス業などの危険が伴う現場だけでなく、lT通信業や旅館業など、さまざまな分野において安全管理者の選任および配置が必要です。そのため、安全管理者の資格を有している人材は需要が高いでしょう。安全管理者は筆記試験と口述試験がありますが、筆記試験は難易度が高く、持っていれば転職や昇給においてもかなり有利な資格です。
◎安全管理者試験の概要
受験資格 | ・大学・高等専門学校の理科系などの専門課程を修了していて、安全に関わる実務経験が2年以上 ・高校で理科系などの専門課程を修了した人で、安全に関わる実務経験が4年以上 |
|---|---|
合格率 | 筆記試験:20~30% 口述試験:80% |
難易度 | ★★★★★ |
試験内容 | ・産業安全一般 ・産業安全関係法令 ・安全(機械・電気・化学・土木・建築から一つ選択) |
マイクロソルダリング(微細はんだ付)技術者
マイクロソルダリングとは、パソコンや家電製品の中に入っている、ミリ単位の細��かい部品や配線をはんだという合金を接着剤のように使ってつなげる技術のことです。この技術を正確に行うスキルを有する人をマイクロソルダリング技術者といいます。
最近では電子機器の小型化が進んでいるため、このマイクロソルダリング技術は必要不可欠であるといえるでしょう。
◎マイクロソルダリング技術者試験の概要
受験資格 | ・インストラクターの経験2年以上 ・工業高等学校以外の高等学校卒業の場合で、経験6年以上 ・工業高等学校卒業の場合で、経験5年以上 ・理工系工業高等専門学校、理工系短期大学または理工系以外の大学卒業の場合で、経験3年以上 ・理工系大学卒業の場合で、経験2年以上 ・上記の各項と同等の能力および経験があると認められる場合 |
|---|---|
合格率 | 84% |
難易度 | ★★ |
試験内容 | 【筆記試験(選択および記述)】 接合理論、材料工学、化学、機械工学、信頼性、評価解析、安全性など全般の専門的知識の確認 【面接試験】 マイクロソルダリング技術に関する専門的な学識とその応用能力の評価水準の確認 |
CAD利用技術資格
CADとはコンピューターを使って設計や製図をするシステムをいいます。主に建築や機械の設計においてよく使われる技術ですが、工場現場でも欠かすことのできないシステムでしょう。CAD作業をするために資格は必須ではありませんが、資格を取得しておくことで、一定水準以上のスキルがあることを証明できます。
CAD利用技術資格には、いろいろな種類のものがあります。
- CAD利用技術者試験(2次元、3次元)
- CADトレース技能審査(建築部門、機械部門)
- Autodeskマスター
- 三次元設計能力検定試験
CAD利用技術者の資格が最も一般的でしょう。
◎CAD利用技術者試験の概要
受験資格 | 【2次元】 なし 【3次元】 1級、準1級:2級を取得していること 2級:なし |
|---|---|
合格率 | 【2次元】 基礎:80% 1級:60% 2級:50% 【3次元】 1級:24.3% 準1級: 52.4% 2級:47.3% |
難易度 | ★★★~★★★★★ |
試験内容 | 【二次元】 CADシステムの概要や基本機能、CADシステムの運用や管理について、ハードとソフト、情報セキュリティと知的財産、三次元CADの基礎知識など 【三次元】 三次元CADデータの活用、三次元CADデータの管理と周辺知識、三次元CADの機能と実用的モデリング手法、三次元CADの概念など |
��機械加工技能士
機械加工とは旋盤、フライス盤、マシニングセンターといった機械を使い、金属材料を加工する作業のことをいいます。金属製品のパーツを作成するときの基本であり必要な作業です。そのため製造工場などでは需要が高いといえます。
機械加工技能士の資格には、3級、2級、1級、特級というレベルに分かれています。この資格を持っていることで、確かな技術を有していることを証明できるため、転職の際にも有利に活用できるでしょう。
◎機械加工技能士試験の概要
受験資格 | 特級:1級合格、5年以上の実務経験 1級:7年以上の実務経験 2級:2年以上の実務経験 3級:特になし |
|---|---|
合格率 | 特級26.6%、1級38.4%、2級25.2%、3級49.6% |
難易度 | ★★★★★ |
試験内容 | 【特級】 ー学科試験ー ・工程管理 ・作業管理 ・品質管理 ・原価管理 ・安全衛生管理および環境の保全 ・作業指導 ・設備管理 ・機械加工に関する現場技術 ・実技試験 ・工程管理 ・作業管理 ・品質管理 ・原価管理 ・安全衛生管理 ・作業指導 ・設備管理 【1級・2級】 ー学科試験ー ・工作機械加工一般 ・機械要素 ・機械工作法 ・材料 ・材料力学 ・製図 ・電気 ・安全衛生 ・選択科目
ー実技試験ー ・選択科目
【3級】 ー学科試験ー ・工作機械加工一般 ・機械要素 ・機械工作法 ・材料 ・材料力学 ・製図 ・電気 ・安全衛生 ・選択科目
ー実技試験ー ・選択科目 |
まとめ
工場勤務者におすすめの国家資格や、民間のおすすめの資格を紹介しました。難易度は資格によってさまざまです。難度が高ければ、取得している人も少ないので合格できればかなり大きなアピールポイントとなり評価もされやすいでしょう。しかし難易度が低いから意味がないのかというと、そうではありません。資格を持っていると正確なスキルを持っている証明になりますし、有資格者と無資格者であれば、有資格者の方が評価され、さまざまな機会に恵まれチャンスをつかみやすいでしょう。自分の仕事内容や希望の転職先に合わせて、資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか。