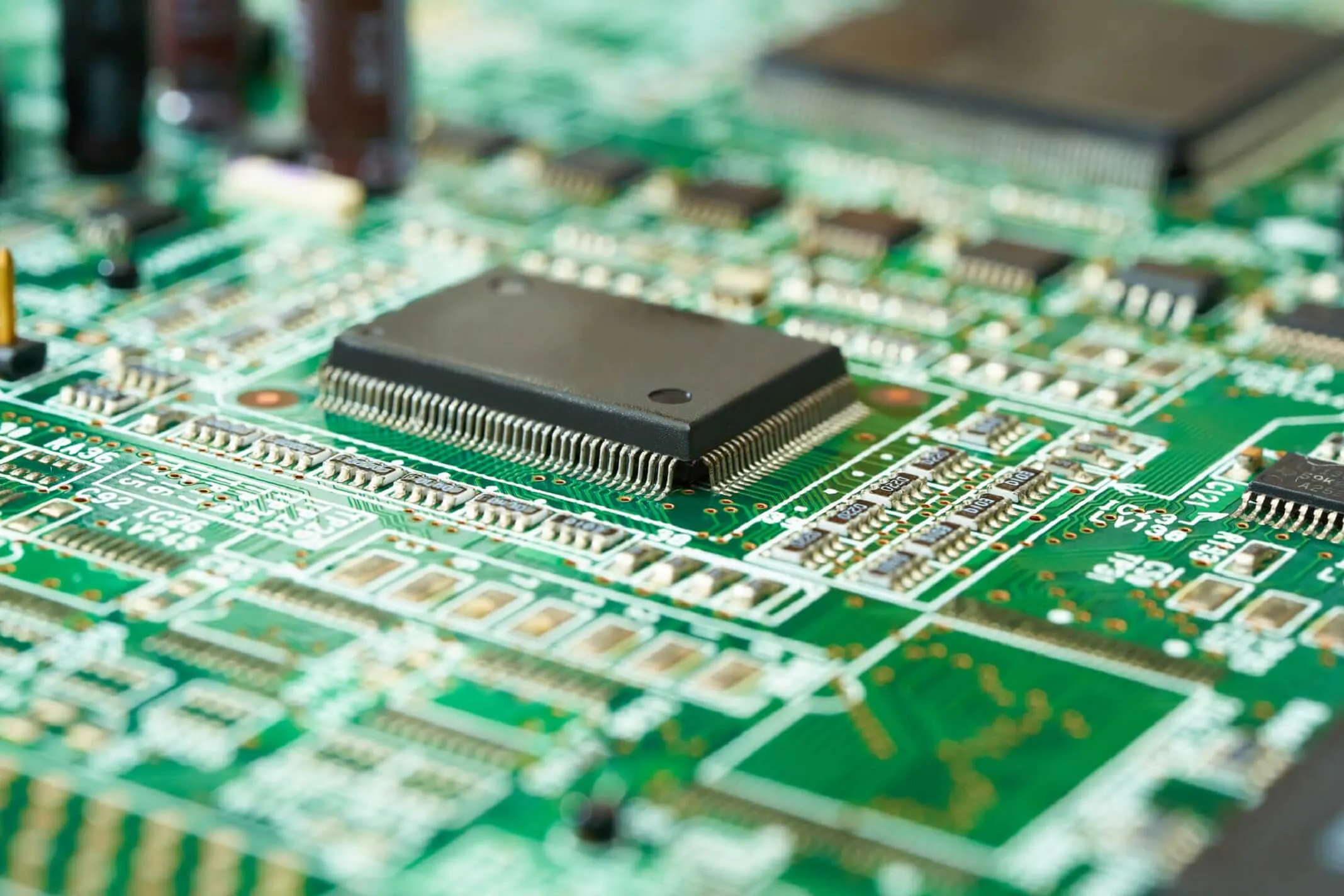研究職はどんな仕事?就職先や働く魅力・就職を有利に進めるポイントも解説

研究職に憧れる方も多いのではないでしょうか。新しい発見を追求し、人類の知識の地平を広げていく - そんなやりがいのある仕事です。しかし、実際の研究職とはどのような仕事なのか、具体的なイメージを持てていない方も少なくありません。
この記事では、研究職の実態や魅力、活躍できる場所、そして研究職を目指すために必要なスキルや準備について詳しく解説していきます。アカデミアから企業の研究所まで、様々な選択肢がある研究職。あなたに合った道を見つけるためのヒントを提供していきましょう。
研究職とは

研究職は、大学や公的機関、民間企業などで新たな知識や技術の創出に携わる専門職です。その活動は主に「基礎研究」と「応用研究」の2つに大別されます。
基礎研究では、これまで誰も発見していない理論やメカニズムの解明に取り組みます。実験による仮説の検証や修正を繰り返し、新たな知見を生み出すことが目的です。一方、応用研究では基礎研究で得られた知見を活用し、具体的な製品やサービスの開発、技術の実用化を目指します。例えば医学分野では新薬の開発、工学分野では新製品の設計や製造プロセスの改善などが該当します。
このように研究職は、純粋な学術的探求から実用的な技術開発まで、幅広い領域で人類の知識と技術の進歩に貢献する重要な役割を担っています。
なお厚生労働省の職業分類表によると、研究職は以下のように分類されています。
- 理学研究者:自然科学の基礎を探求する研究者
- 工学研究者:技術や工学分野の研究を行う専門家
- 農学・林学・水産学研究者:農業、林業、水産業に関連する研究を行う専門家
- 医学研究者:医療や健康に関する研究を行う専門家
- 人文科学研究者:文学、哲学、歴史など人文科学分野の研究者
- 社会科学研究者:社会学、経済学、政治学など社会科学分野の研究者
- 他に分類されない研究者:上記以外の分野で研究を行う専門家
これらの分類は、研究者の専門分野に応じて定められています。
参考:厚生労働省|職業分類表[2]
研究職の就職先

研究職の就職先は、多岐にわたります。主な就職先としては、以下のものが挙げられます。
- 大学
- 国や地方自治体の研究所
- 民間企業
大学
大学における研究職は、主に基礎研究に重点を置き、新たな理論や原理の発見・解明を目指す場です。一般的なキャリアパスとしては、博士号取得後にポストドクター(ポスドク)として研究活動をスタートさせます。
研究プロジェクトへの参加や独自のテーマ追求を通じて実績を積み、その後「助教」「准教授」「教授」といったアカデミックポジションを目指していきます。大学では研究活動に加えて教育活動も担うため、次世代の研究者育成という重要な役割も果たしています。
国や地方自治体の研究所
国や地方自治体が設置する研究機関は、公共の利益に資する研究開発を担う重要な機関です。国立感染症研究所や科学警察研究所といった国立研究機関、また地方自治体が運営する産業技術センターや健康安全センターなどがこれにあたります。
これらの機関では営利を目的とせず、社会的課題の解決や科学技術の発展に向けた先進的な研究開発に取り組みます。感染症対策や犯罪捜査技術の向上など、それぞれの機関の目的に応じた研究テーマに取り組み、基礎研究から応用研究まで幅広い研究活動を展開しています。国立研究機関では国家公務員として、公設試験研究機関では地方公務員として働くことができます。
民間企業
民間企業の研究所では、企業の競争力強化や利益創出に直結する研究開発が中心です。主に自社製品やサービスの開発・改良に関わる研究を行い、市場ニーズに応える革新的な技術の実現を目指します。
研究の性質は企業によって異なり、製薬会社のように新薬開発のための基礎研究に力を入れる企業もあれば、自動車メーカーのように既存技術の応用や改良を重視する企業もあります。ただし、いずれの場合も研究成果の事業化や収益化が重要な目標となるため、市場動向や経営戦略と密接に連携しながら研究活動が進められます。
【関連記事】研究職のキャリアプランを就職先・研究内容別に紹介!身につけるべきスキルも解説
研究職に就職するメリット3つ

研究職に就職するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 自分が興味のある分野に関われる
- 大きなやりがいを得られる
- 年収が高い
自分が興味のある分野に関われる
研究職の魅力の一つは、自分が深く興味を持つ分野や学問に携われることです。探究心や知的好奇心を持って、最先端の領域に挑戦し、新たな発見や知見を生み出していくことができます。
自分の関心事が直接仕事につながることで、日々の研究活動に情熱を持って取り組むことができ、それが大きなモチベーションとなります。また、専門分野での研究を通じて、論理的思考力や問題解決能力を磨きながら、研究者としての成長を実感できることも、研究職ならではの魅力と言えるでしょう。
大きなやりがいを得られる
研究職には、社会に大きな影響を与えられる魅力があります。新薬開発による医療の進歩、技術革新による生活の質の向上、環境問題への解決策の提示など、研究成果が人々の暮らしをより良いものへと変えていく可能性があるのです。
たとえ基礎研究であっても、その知見が将来の技術や産業の発展の土台となり、社会の進歩に貢献できるかもしれません。自分の研究が人類の課題解決や生活向上に直接的・間接的に役立つという実感は、研究者ならではの大きなやりがいといえます。
年収が高い
研究職、特にバイオテクノロジー分野の研究者は、高い専門性と技術力が評価され、比較的高い年収を得られる傾向です。具体的には、バイオテクノロジー研究者の平均年収は740.2万円(*1)と、日本の全職種平均年収である約460万円(*2)を大きく上回っています。
これは、高度な学術知識や研究スキル、革新的な成果を生み出す能力に対する評価の表れと言えます。また、研究成果が企業の競争力や収益に直結する場合も多く、それに見合った待遇が提供されていることを示しています。ただし、この数値は経験年数や研究分野、勤務先の規模などによって変動することにも留意が必要です。
参照:(※1)厚生労働省「jobatag」
(※2)国税庁|令和5年分 民間給与実態統計調査
【関連記事】
研究職の平均年収は約720万!収入に影響する4つのポイントも公開
研究職の年収は1000万超えできる?実態や到達するためのポイントを解説
研究職に就職するデメリット2つ
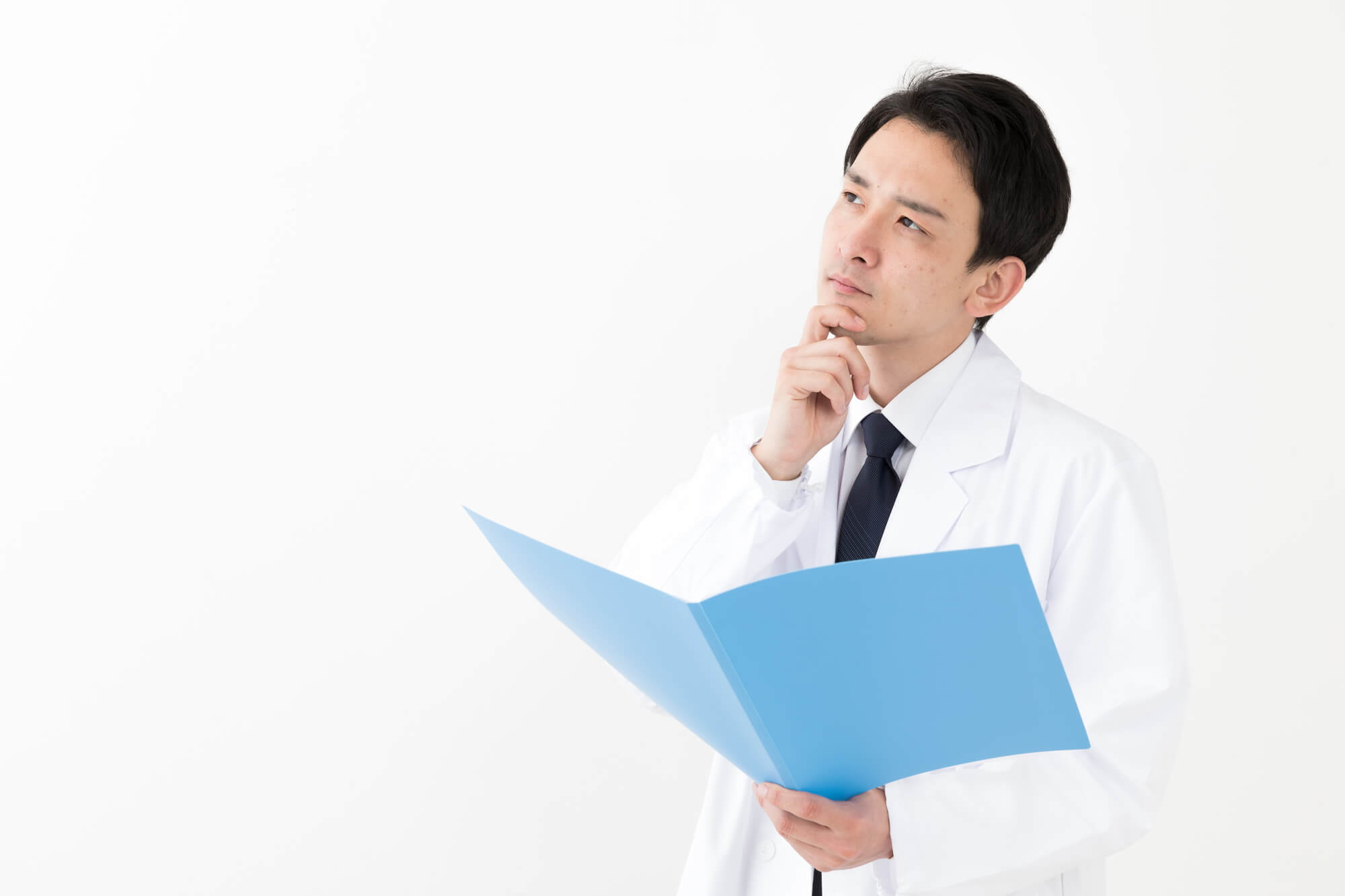
研究職に就職するデメリットとして、以下の2つが挙げられます。
- 他業種へ転職しにくい
- 研究成果を求められる
他業種へ転職しにくい
研究職は一つの専門分野を深く追求する職種であるため、他業種への転職には独特の課題があります。長年にわたって特定の研究分野に特化した経験を積むことで、その分野では高い専門性を持つ一方で、一般的なビジネススキルや他分野の経験を積む機会が限られがちです。
そのため、研究職から営業職や企画職といった異なる職種へのキャリアチェンジを考える際には、新たなスキルの習得や経験の積み直しが必要となることが多く、転職までに時間と労力を要する傾向にあります。
ただし、研究職で培った論理的思考力や問題解決能力は、他の職種でも十分に活かせる強みとなり得ます。
【関連記事】研究職の転職が難しい理由は?おすすめの転職先9選と未経験業界に転職するコツ
研究成果を求められる
研究職では、研究成果を出すことへのプレッシャーが大きな課題です。特に民間企業では、研究費用や人件費などの投資に見合う成果が求められ、期待される結果を出せない場合はプロジェクトの打ち切りや配置転換を迫られる可能性もあります。
また、研究には予期せぬ困難や失敗がつきものであり、思うように進展しないことも多いです。それでも期限内に成果を出すことが求められ、常に結果を意識しながら研究を進めていく必要があります。このような成果主義のプレッシャーは、研究者の精神的な負担となることもあり、研究職特有の課題といえるでしょう。
研究職に向いている人の特徴

研究職に向いている人は、以下のような特徴を持つ人が多いです。
- 探究心を持ってコツコツと努力できる
- 失敗を前向きに捉えられる
- コミュニケーション力に長けている
探究心を持ってコツコツと努力できる
研究職では「なぜ?」「どうして?」という知的好奇心を持ち続け、一つのテーマを長期的に追求することが求められます。時には地道な実験や検証の繰り返しが必要となりますが、その過程を楽しみながら粘り強く取り組める人が向いています。
また、興味が移りやすい人よりも、一つの課題に対して腰を据えて取り組める姿勢が重要です。
失敗を前向きに捉えられる
研究では、思い通りの結果が得られないことが頻繁にあります。しかし、その失敗を単なる挫折とせず、新たな発見のチャンスや改善の機会として捉えられる姿勢が大切です。
失敗から学び、それを次の仮説や実験に活かせる柔軟な思考と、諦めない心構えを持っている人が研究職に適しています。
コミュニケーション力に長けている
研究は一人で行うものではありません。チームでの共同研究や、他部門との連携、研究成果の発表など、様々な場面でコミュニケーションが必要です。
自分の研究内容を分かりやすく説明できる力や、異なる専門分野の研究者と円滑に情報交換できる対話力を持っている人が、研究職で成功しやすいと言えます。
研究職への就職を有利に進めるためのポイント

研究職への就職を有利に進めるためのポイントは、主に以下の点が挙げられます。
修士号・博士号を取得する
研究職を目指す上で、修士号や博士号の取得は大きなアドバンテージです。特に大学の研究職や公的研究機関では、これらの学位が必須の応募要件となっていることが多く、学部卒では門戸すら開かれないケースがあります。
民間企業の研究職でも、高度な専門知識や研究能力の証明として、大学院での学位が重視されます。修士号・博士号を取得することで、専門分野での研究経験を積み、より深い知識と実践的なスキルを身につけることができます。これらは研究職としてのキャリアを確実なものにする重要な足がかりとなるでしょう。
研究実績を積んでおく
研究職の採用において、研究実績は応募者のスキルやポテンシャルを直接的に示す重要な指標です。学会での発表経験や論文執筆、研究プロジェクトへの参加など、具体的な実績があることで、研究に必要な専門知識や実践的なスキルを持っていることを証明できます。
そのため、学生時代から積極的に研究活動に取り組み、自身の専門分野における実績を積み重ねていくことが推奨されます。
また、研究を通じて培った専門性は、入社後の即戦力としても評価され、採用選考での大きなアピールポイントとなります。特に、志望する企業や機関の研究領域に関連する実績があれば、より説得力のある自己アピールが可能となるでしょう。
研究以外の勉強もきちんと行う
研究職を目指すなら、専門分野の研究に加えて、英語力の向上に特に力を入れることが重要です。近年、研究活動のグローバル化が進み、海外の研究者との交流や英語論文の読解・執筆が日常的に求められるようになっています。
実際に、多くの企業が研究職の採用条件としてTOEICスコアを設定しており、例えば700点以上を要求するケースも少なくありません。このような要件をクリアするためにも、学生時代から英語学習を計画的に進め、実践的な英語力を身につけておくことが、研究職への就職を有利に進める重要なポイントとなります。
研究職に関するよくある質問

ここからは、研究職に関してよくある質問に回答していきます。
研究職は勝ち組ですか?
研究職が「勝ち組」かどうかは、個人の価値観によって異なります。メリットとしては、知的好奇心を満たせること、研究成果による社会貢献、専門性の活用、比較的安定した収入などが挙げられます。
一方でデメリットとしては、研究費や職位を巡る厳しい競争、任期付き雇用による不安定さ、継続的な成果が求められるプレッシャー、ワークライフバランスの崩れやすさなどがあります。
そのため、研究職を選択する際は、これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、自身の価値観や希望するキャリアパスに照らして判断することが重要です。
研究職は文系でもなれますか?
文系出身者が研究職に就くことは一般的に難しい状況です。これは、多くの研究職が理系分野の専門知識やスキルを必要とするためです。
ただし、経済学や社会学といった文系分野の研究、マーケティングリサーチャー、UXリサーチャー、図書館情報学の専門家、人文系の学芸員など、文系出身者でも活躍できる研究職は存在します。これらの職種に就くためには、大学院での専門性の深化や、統計学やデータ分析などの必要なスキルの習得が重要となります。
まとめ
研究職は、成果が求められる厳しい環境でありながら、社会に大きな貢献ができ、自分の興味や専門性を存分に活かせるやりがいのある職業です。就職への道のりは決して容易ではありませんが、早期から研究分野を定め、修士号・博士号の取得や研究実績の積み重ね、英語力の向上など、計画的な準備を進めることで道は開かれます。
ワールドインテックのRD事業部は、経験や適応に応じた職種への就業、エリア希望や家庭の都合における勤務地・通勤の考慮など働きやすい環境を提供しています。
研究職でより高みを目指したいと考えている方は、ぜひワールドインテックに応募してみてください。