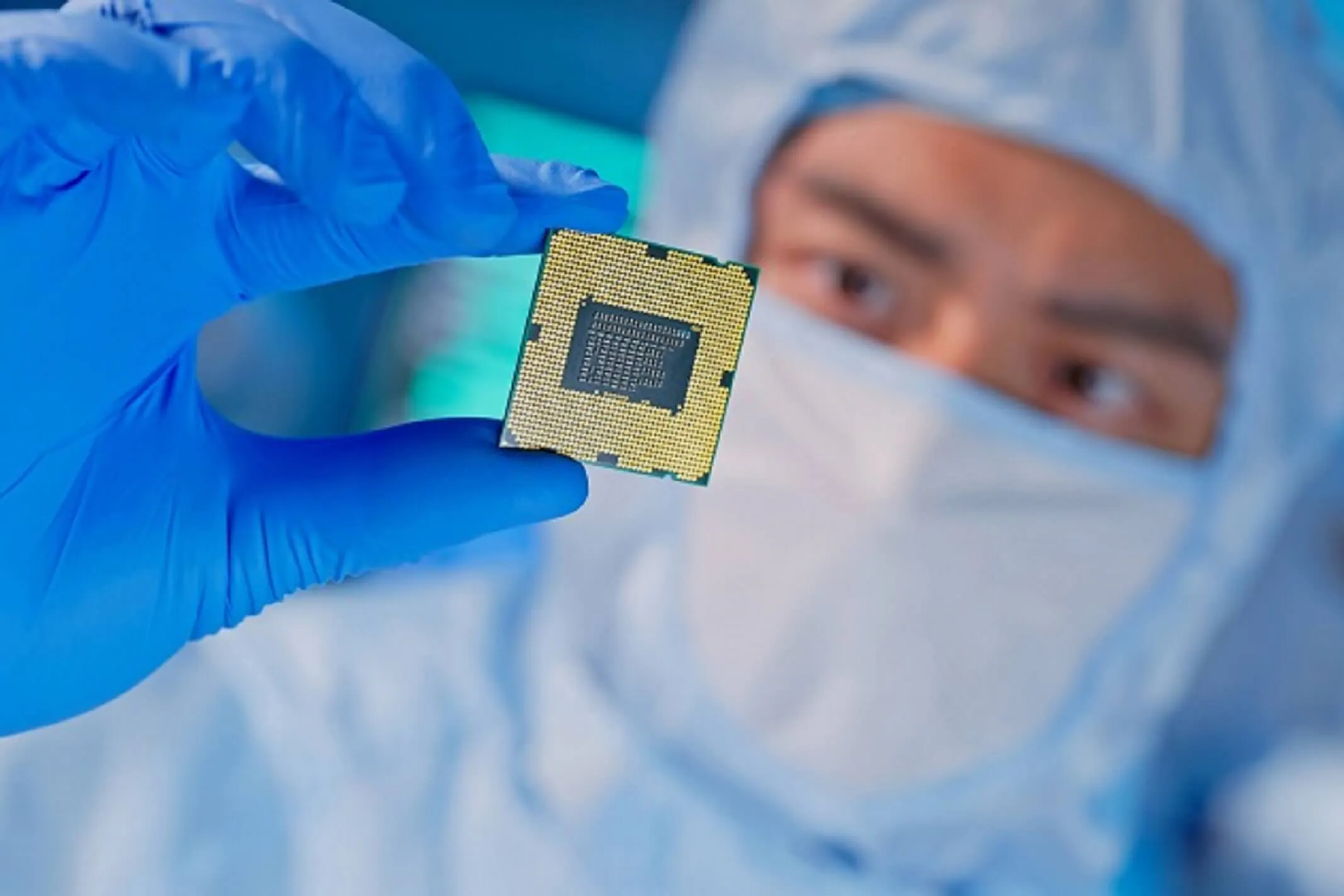製薬会社の研究職になるには?就職するために求められるスキルや平均年収を解説

「製薬会社の研究職の仕事内容は?」
「製薬会社の研究職に求められるスキルを知りたい」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
製薬会社の研究職の仕事内容は、専門性や分野ごとに幅広く分かれています。専門性が高く求められるスキルも多いため、就職難易度は高いです。
本記事では、製薬会社の研究職の仕事内容や求められるスキルについて解説します。向いている人の特徴についても解説しますので、研究職への転職をご検討の方は、ぜひ最後までお読みください�。
【関連記事】研究職はどんな仕事?就職先や働く魅力・就職を有利に進めるポイントも解説
製薬会社の研究職の仕事内容

製薬会社の研究職には幅広い業務があり、新薬の初期段階から臨床試験、市販後の評価まで幅広い業務が存在します。
製薬会社の研究職は、専門分野によって以下に細分化される点も特徴です。
- 薬理研究:薬の作用や効果を研究する
- 毒性研究:薬の安全性を評価する
- 製剤研究:薬の投与方法や剤形を研究する
- 分析研究:薬の成分や品質を分析する
- バイオインフォマティクス研究:ゲノムやタンパク質の情報を解析する
製薬会社の研究職では1つの新薬を開発するために、さまざまな専門分野に分かれて研究を行っています。
以下の章では具体的な研究分野と仕事内容を解説しているので、1つずつ見ていきましょう。
基礎研究
基礎研究は、製薬会社の研究職において極めて重要な役割を果たしており「ターゲット探索」「バリデーション」の2つが主な仕事です。
ターゲット探索は、ターゲットとなる分子や経路を特定し、疾患においてどのような役割を果たすかを評価します。バリデーションは、新薬の製造工程や方法が正しいかどうかを検証するために行う一連業務のことです。科学的根拠や妥当性があるかを調査し、報告します。
基礎研究の内容や成果は、後に行う臨床試験や製品化に大きく影響するため非常に重要な分野です。したがって研究者は科学的な知識に加えて、高度な分析力と問題解決能力が求められます。
非臨床研究
非臨床研究は、人に対する試験を行う前に動物を使って必要な科学的データなどの研究を行います。
非臨床研究の具体的な仕事内容は、以下の3種類です。
- 薬効薬理試験:ターゲットの疾患に対する薬の効果や作用機序を評価する
- 安全性試験:薬剤による副作用や有害事象を特定する
- 製剤研究:薬剤の投与方法や剤形を考える
非臨床研究は、科学的な根拠に基づく新薬の開発を促進し、最終的な臨床試験へとつながる重要なステップです。非臨床研究をきちんと行うことで薬剤の効果と安全性を確保し、患者に高品質な医薬品を提供できます。
臨床開発
臨床開発は、新薬を人に投与して安全性や効果を確認する仕事です。臨床試験は新薬開発のプロセスにおいて非常に重要なため、通常は複数の過程に分けて行います。
- 第一相試験:適切な投与量を調査し安全性を確認する
- 第二相試験:薬の有効性を評価しさまざまな疾患に対する効果を確認する
- 第三相試験:大規模なデータを基に薬の効果と安全性を確立する
各試験で得られたデータを基に、新薬の市場導入に向けて最終調整を行います。
また臨床開発では、得られた結果を基に薬事申請を行わなければなりません。薬事申請の内容次第で国から認可が降りるかどうかが変わりますが、人々の健康や生命維持に大きく影響するため、臨床開発の研究者には法令遵守や品質管理に対する高い意識が求められます。
【関連記事】臨床開発職に向いている人とは?製薬会社の開発職に必要な能力や多い出身学部を解説
市販後調査
市販後調査は、新薬が流通し人々の手に渡った後に効果や副作用などを調べます。市販後調査を行うと、臨床試験では確認できなかった長期的な副作用や特定患者の反応が明らかになり、新薬のリスクや効能の把握が可能です。
なお市販後調査で得られたデータは規制当局に提出され、必要に応じて製品ラベルに警告が追加されたり使用計画が見直されたりする場合があります。
市販後調査は、新薬の信頼性を維持するために不可欠なプロセスです。そのため製薬会社は、新薬の流通後も責任感を持って対応に当たる必要があります。
【関連記事】製薬会社の仕事内容とは?特徴や求められるスキルについても解説!
製薬会社の研究職の平均年収

厚生労働省のデータによると、薬学研究者の平均年収は740.2万円で、日本の平均年収である約460万円と比較すると高水準です。
具体的な年収は、経験年数や役職、企業の規模によって異なるため一概には言えませんが、製薬会社の研究職は高い専門性と技術力が求められるため、年収も比較的高いと予想できます。
参照:jobtag|薬学研究者
具体的な職種の平均年収を知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてお読みください。
【関連記事】
製薬会社の職種別平均年収|製薬会社に転職するには
製薬会社の職種別平均年収と年収ランキング|製薬会社に転職するには
製薬会社の研究職になるには?

製薬会社の研究職として働くには、高度な専門知識と研究能力が必要不可欠です。そのため大学院まで進学し、修士号、博士号の取得が求められます。
進学して修士号、博士号を取得するだけでなく、入社後に即戦力として活躍できるよう以下の分野を専門的に学ぶのが重要です。
- 薬学
- 医学
- 生物学
- 化学など
また研究職はチームでの研究、開発も多いため、コミュニケーション能力や協力的な姿勢も身につけておきましょう。
【関連記事】製薬会社で働くには?就職対策・年収・向いている人の特徴を紹介
製薬会社への就職が難しいと言われるのはなぜ?

製薬会社の就職は難易度が高いと言われています。理由は以下の3つです。
- 専門性が高い
- 規制や品質管理が厳しい
- 製薬業界は競争が激しい
1つずつ解説します。
専門性が高い
製薬会社への就職が難しいと言われる理由として、求められる専門性の高さが挙げられます。
新薬の開発には長い年月と膨大な費用がかかるため、企業は投資対効果を確保するべく優秀な人材を厳選して採用する必要があるからです。
新薬の開発プロセスは非常に複雑で、基礎研究から非臨床試験、臨床試験、市販後の評価まで、多岐にわたります。各段階で専門的なスキルが求められるため、企業は十分な学歴や実績を持つ候補者を探す傾向にあります。したがって製薬業界では高い専門性を持っていないと就職するのは難しいです。
さらに近年は医療の進展に伴い、MR(医薬情報担当者)などの研究職以外の職種でも、医薬品に関する専門的な知識が求められるようになっています。そのため従来よりも中途採用のハードルが上がっているのが現状です。
製薬会社への転職を目指しているなら、高度な専門性を持っているとアピールできるよう、資格や実績を積んでおく必要があります。
規制や品質管理が厳しい
医薬品は人命に直接関わるため、国や国際機関による厳しい基準が設けられています。
たとえばGQP(医薬品などの品質管理の基準)やGVP(医薬品などの製造販売後安全管理の基準)など遵守しなければ、新薬の製造、販売はできません。
厳しい基準に対応できるスキルや専門性が求められるため、製薬会社の研究職への就職は難しいと言われているのです。
また製薬業界は医薬品の一貫性や信頼性を確保するために、厳密な試験や評価を行う必要があります。厳しい検査をクリアするには、やはり専門的な教育やトレーニングを受けた人材の確保が重要です。
製薬業界は競争が激しい
製薬業界の競争が激しい理由は、業界革新が求められているからです。
新薬の研究開発は時間がかかるだけでなく投資も巨額なため、市場での成功を果たすには、他社よりも確実に成果を挙げる必要があります。継続的に成果を挙げるには優れた研究者や開発者が必要なため、求人倍率が高くなり、就職難易度も上がるのです。
また製薬業界は新薬を製造し申請が認められれば特許を取得できますが、有効期限は最大で25年です。特許が切れると他の企業も製造が可能になるため、利益が減少するおそれがあります。
そのため企業は継続的に新しい薬を開発し続けなければならず、研究職には常に最新の知識や技術を持った人材が求められます。
製造業界は競争が激しいですが、専門知識や実務経験を持つ人材への需要は非常に高いです。製造業界へ就職を叶えるなら、スキルや実績を携えたうえで企業へアピールしましょう。
製薬会社の研究職が求められるスキル

製薬会社の研究職に求められるスキルは、以下の7つです。
- 実験スキル
- データ解析能力
- 計画立案能力
- 論理的思考力
- 問題解決能力
- 英語力
- 情報収集能力
1つずつ解説しますので、自分はどのスキルを身につけるべきか、伸ばせば良いのかの参考にしてみてください。
実験スキル
実験スキルは、新薬の開発や評価において、正確で信頼性のあるデータを得るために不可欠です。具体的には以下が該当し、研究内容に応じた高度な実験技術が求められます。
- 細胞培養
- 遺伝子操作
- タンパク質解析
- 動物実験など
実験で得た内容は、新薬の開発や効果に大きく影響します。そのため研究者は常に技術を磨き、最先端の実験スキルを身につけるのが大切です。
データ解析能力
データ解析能力は、実験から得られたデータを正確に処理し、価値のある情報を引き出すために不可欠です。具体的には以下が該当し、多岐にわたる技術が求められます。
- 実験データの統計解析
- データマイニング
- バイオインフォマティクスなど
データ解析能力は製薬会社の研究職において重要なため、情報を効果的に処理し解釈する能力が必要です。
計画立案能力
計画立案能力は、複雑な問題を論理的に分析し、実行可能な解決策を見出すために必須です。新薬の開発プロセスは多岐にわたるため、適切な計画を立てることで効率的に進行できます。
計画立案能力を活かせる場面は、主に以下のとおりです。
- 初期段階:新薬開発に向けた目標を設定、具体的な手順やスケジュールの策定
- 実験・臨床段階:課題に直面した際の原因分析、条件見直し、スケジュールの確認変更
新薬開発は長期プロジェクトのため、綿密なスケジュール設定や、トラブル発生時の対応力などが求められます。そのため計画立案能力があれば製薬業界で活躍できるでしょう。
論理的思考力
論理的思考力は、複雑な問題を効果的に分析し、適切な解決策を見出すために必要です。論理的思考力が身につくと、研究で直面するさまざまな課題に対して、より効果的にアプローチできるようになります。
研究過程では、期待する結果が得られない場合が多いです。思うような成果が得られない際、論理的に状況を分析して原因を明らかにする能力が求められます。たとえば実験条件や使用した材料に原因があれば、次に取るべき行動がわかります。
また論理的思考力は、チーム内でコミュニケーションを取る際にも有効です。研究職では異なる専門知識を持つメンバーと協力して課題に取り組むため、論理的に自分の意見を伝えられると研究をスムーズに進められるでしょう。
問題解決能力
研究過程では、予期せぬ問題や課題が起こりやすいため、トラブルやアクシデントに柔軟に対応できる能力が必要です。
たとえば実験結果が期待と異なる場合、原因を特定するためにデータを詳細に確認し、条件を再評価しなければなりません。この際柔軟な思考があると、従来の方法にとらわれずに新しいアプローチを提案できるでしょう。
また問題解決力は、チーム内でのコミュニケーションにも役立ちます。チーム内で異なる意見を持つ人が現れた場合、双方の意見を聞いて最善の方法を提案できるからです。
研究職として働くなら、問題を正確に把握しさまざまな視点から解決策を提示する力を養いましょう。
英語力
研究や開発に使用する論文や資料は英語で書かれている場合があるため、英語力は欠かせません。また学会発表などの場でのコミュニケーションは、基本的に英語です。
また英語力は論文執筆の際にも必要なため、読む、話す、書くのすべてで英語スキルが求められます。
研究職として国際的な環境で活躍するには、日々の学習を怠らずに英語力を向上させる努力をしましょう。
情報収集能力
研究者は常に最新の研究動向や技術情報を収集し、日々の研究に活かす必要があります。
製薬業界は新たな治療法や技術の開発など、急速に進化しています。変化に迅速に対応しスキルとして反映するには、最新の関連文献やデータを把握しなければなりません。
また研究職は学術雑誌、国際会議、オンラインデータベースなど、さまざまなプラットフォームから必要な情報を取得しなければなりません。情報は膨大なため、正しい情報だけを認識する取捨選択能力も求められます。
知識のインプットを怠らず、常に最新の情報を収集するように心がけましょう。
【関連記事】製薬会社の就職・転職に必要な資格とは?職種ごとに詳しく解説
製薬会社の研究職が向いている人の特徴

製薬会社の研究職が向いている人の特徴は、以下の4つです。
- 科学的好奇心や探求心がある
- 根気強さと集中力がある
- コミュニケーション能力に優れている
- 倫理観と責任感が強い
1つずつ解説します。
科学的好奇心や探求心がある
新しい知識を習得したり技術に挑戦したりすることに喜びを感じる人は、研究職として成功しやすいです。
科学的好奇心は、新薬の開発や改善に役立ちます。研究者は新しい治療法や薬剤の開発を目指して実験を行いますが、プロセスの過程では多くの疑問や課題に直面するでしょう。しかし好奇心が旺盛であれば、新しい視点から問題を解決できる可能性があります。
また探求心があれば、研究に行き詰まっても解決策を模索する力が湧くでしょう。
好奇心や探究心は一見研究職との関わりが薄く見えますが、実は非常に重要な要素です。
根気強さと集中力がある
医薬品の研究開発は長期間にわたるため、想像もしないトラブルが起こる可能性があります。研究者として仕事を進めるには、トラブルやアクシデントに負けない根気強さと集中力が必要です。
研究は短期間で簡単に結果を出せるものではありません。実験中に良い結果が得られなかった場合は挫折を感じますが、諦めずに根気強くデータを分析して何度も挑戦すれば、意外な解決策が見つかるでしょう。
また研究職は長期間にわたって複雑な実験やデータ解析を行うため、集中力が必要です。研究中に注意散漫になると、ミスや見落としが発生しやすくなります。高い集中力の維持は、正確な結果を得るためには欠かせません。
長期にわたる研究開発を粘り強く続け、集中して取り組むことができる人が、研究職として活躍できます。
コミュニケーション能力に優れている
研究開発はチームで行われる場合が多いため、コミュニケーション力がある人に向いています。
研究職はチーム内に実験結果や進捗状況を正確に報告し、問題や課題を共有しなければなりません。明確な言葉で自らの意見や発見を仲間に伝えられると、共通の意思を持って目標に向けて効率的に作業を進められます。
また研究職は、他部門との連携も重要です。たとえば製品の実用化に向けて、製造部門やマーケティング部門と密接に連携する必要があります。
異なるバックグラウンドを持つ人に対して円滑にコミュニケーションを取れれば、プロジェクトの一貫性が保たれ、より質の高い成果を生み出せるでしょう。
倫理観と責任感が強い
医薬品の開発は人々の健康に大きく関わるため、倫理観と責任感の強さが重要です。
新薬の開発は、患者の安全や効果を最大限に考慮しなければなりません。したがって研究者は自己の利益でなく、患者の健康に配慮した判断を下せる倫理観が求められます。
また医薬品開発は長期的なプロジェクトのため、多くの資源と時間が投入されます。長期間プロジェクトをやり抜く責任感がある人は、研究職として活躍できるでしょう。
製薬会社の研究職は、人々の命と健康を預かっているという意識を常に持って仕事に当たる必要があります。
まとめ
製薬会社の研究職の仕事内容は基礎研究から臨床、市販後調査まで多岐にわたります。研究職は高収入を目指せる仕事ですが、求められるスキルや専門性が高いです。
また企業は優秀な人材を求める傾向にあるため、就職して活躍するにはスキルや知識のアップデートが欠かせません。
本記事で紹介している求められるスキルや向いている人の特徴を参考に、研究職への転職を検討してみてください。
ワールドインテックのRD事業では、経験や適応に応じた職種への就業、エリア希望や家庭の都合における勤務地・通勤の考慮など働きやすい環境を提供しています。
研究職でより高みを目指したいと考えている方は、ぜひワールドインテックに応募してみてください。